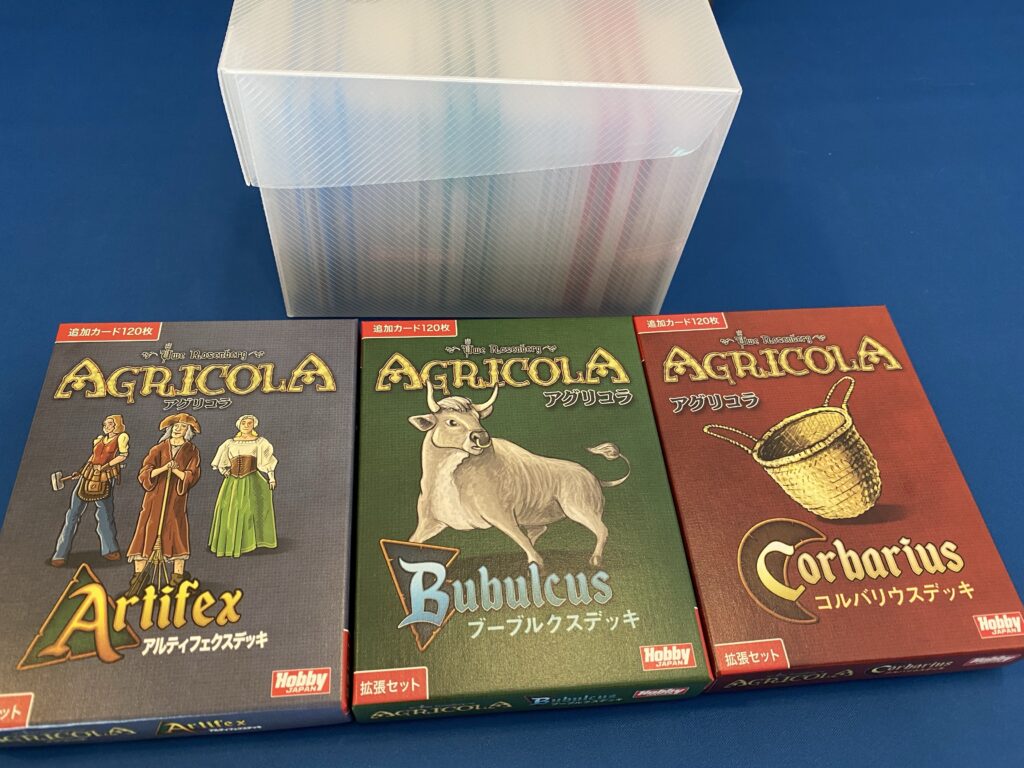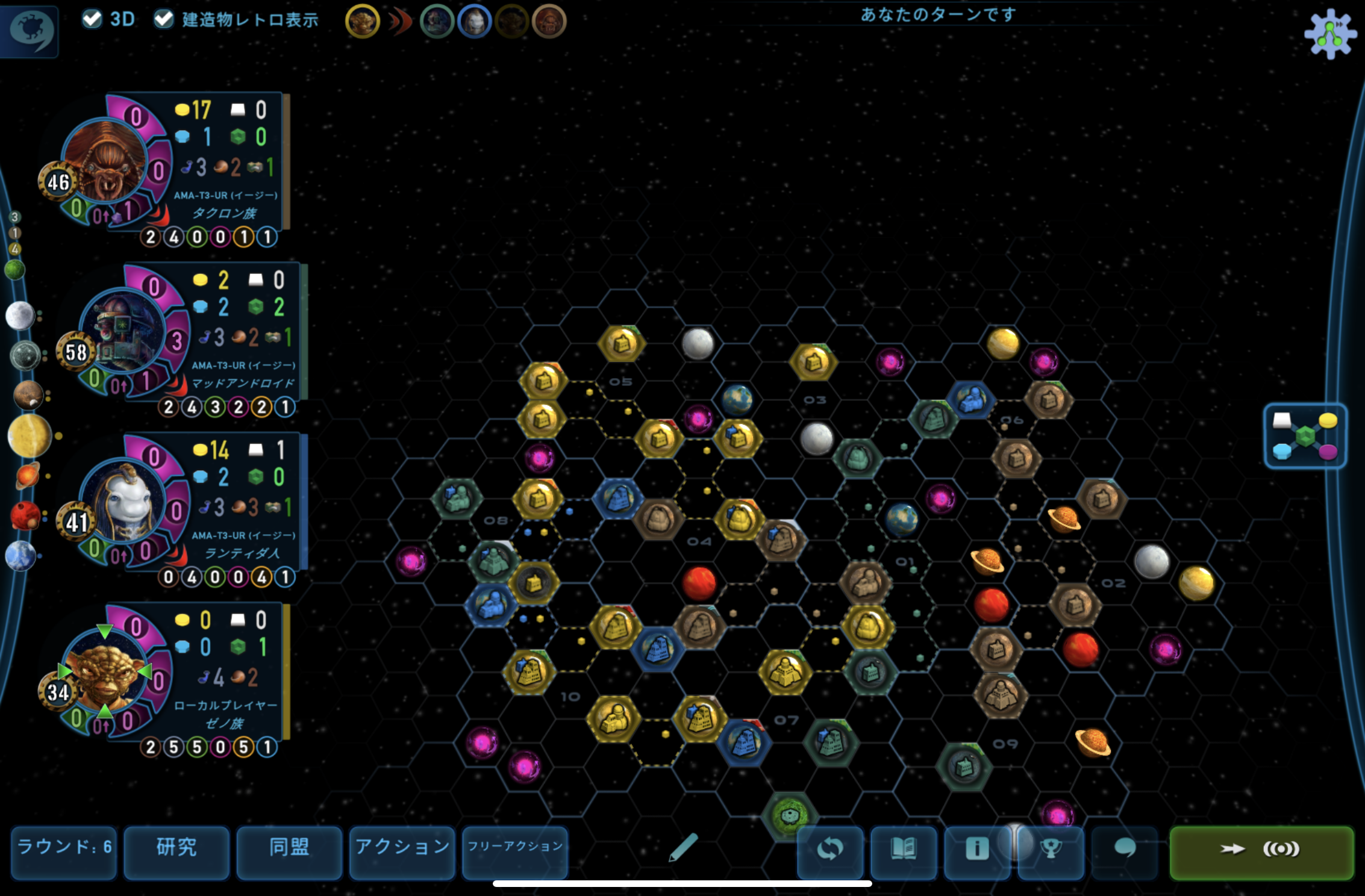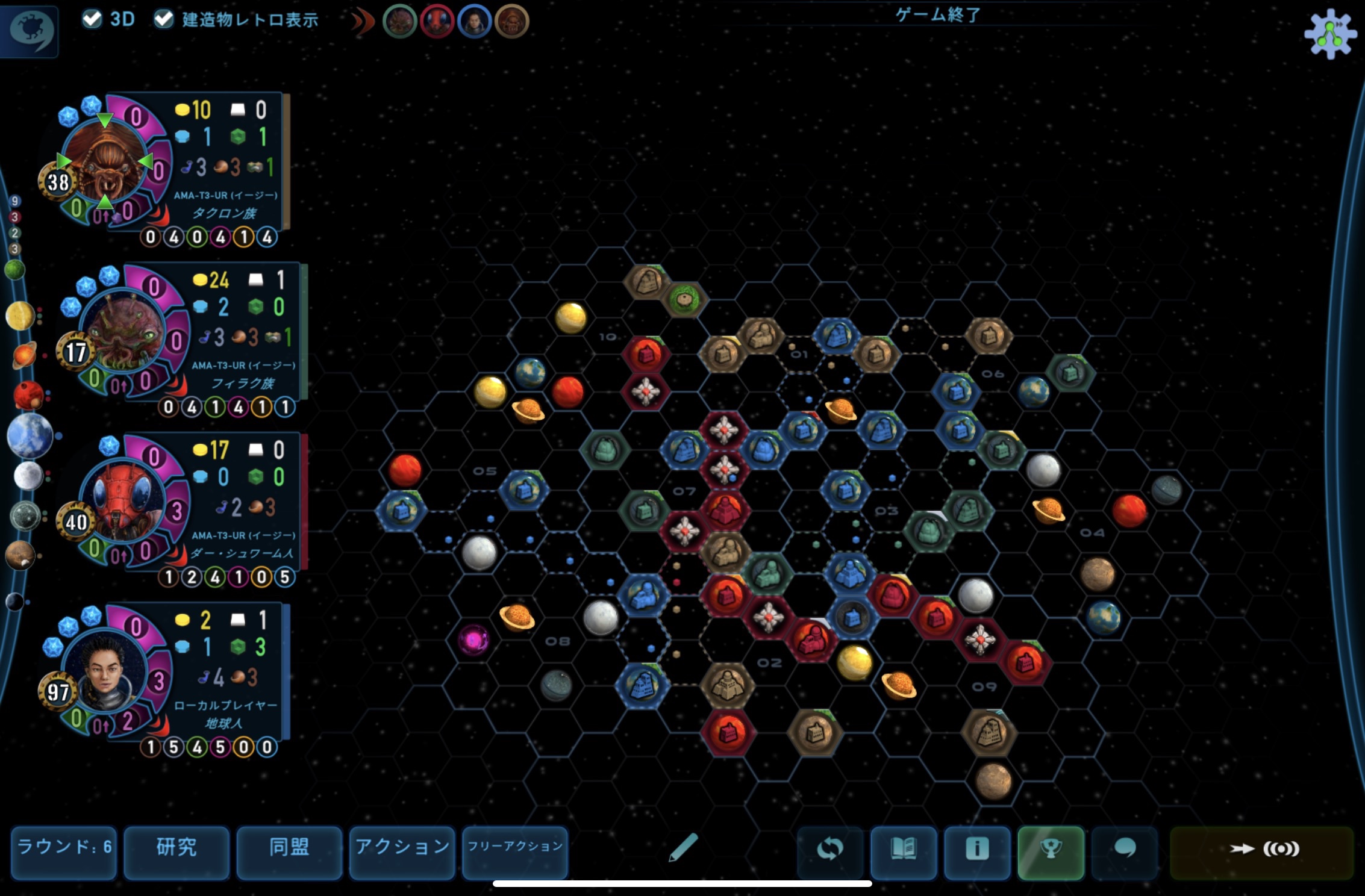『アグリコラ』拡張と一緒に購入したものを開封しました。
レムルース
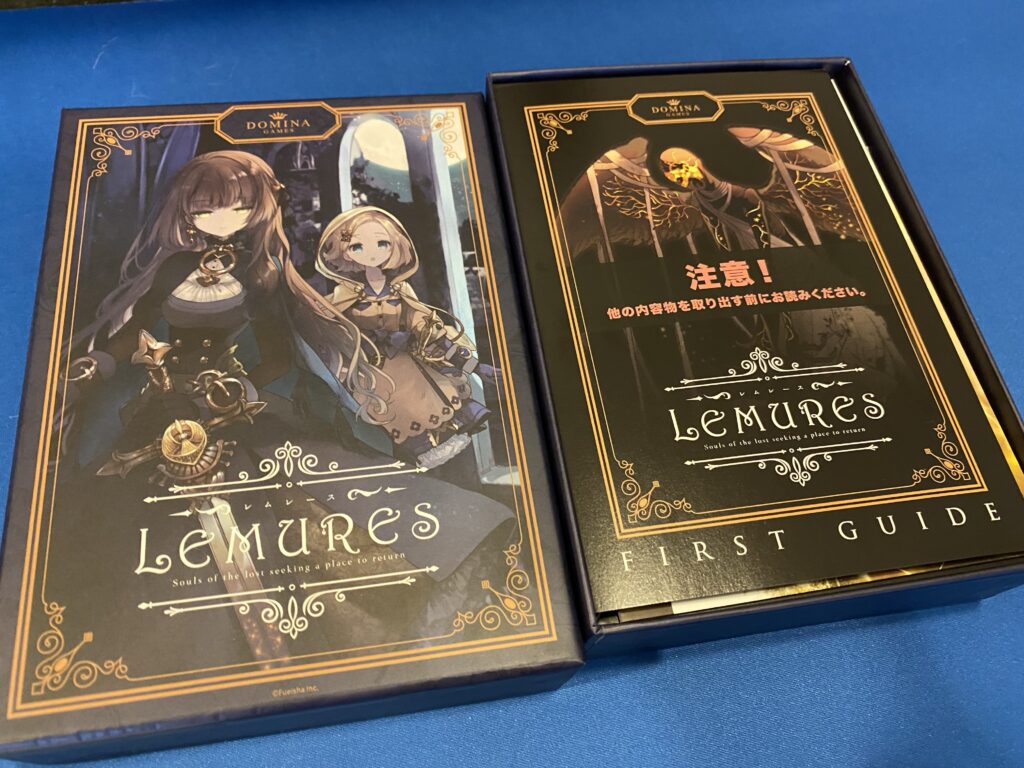
前にも紹介した『GEMINOA』と同じデザイナーが手掛けた『レムルース』。
- デッキ構築
- デッキ圧縮
- ダンジョン探索
と、比較的小さめな箱に収められているのにプレイ時間は60〜90分という重量級です。
概要
プレイヤーはカードをめくりながらイベントや精霊と出会っていき、合間合間に自分のデッキを構築しながらボスとの戦いに臨みます。
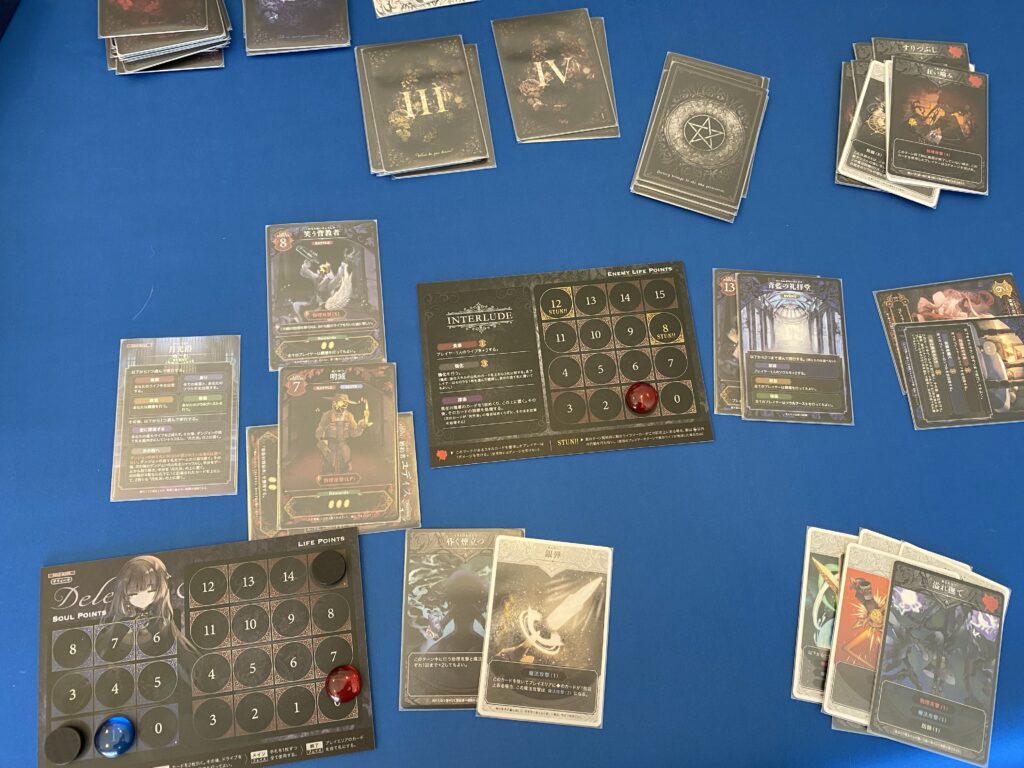
途中に出会う敵はめっぽう強く、苦戦は必至。そこで得られる報酬(ジェム)によりライフを回復したりカードを強化していきます。
感想

「極めて難しい」に尽きます。
- エンカウント率が異様に高く
- 後半になればなるほど異様な攻撃力と防御を持ち
- こちらのライフ回復手段が乏しい
- その回復をしすぎるとカードの強化ができなくなる
と、異様なジレンマに悩まされます。最初のうちは第一階層の突破すらままならないでしょう。
それ故に敵を倒したときの感動は得難いものとなっていますし、強化したカードの戦略もだんだんと学んでいけます。
初プレイは最初の階層のボスでゲームオーバー。2回目は次の階層で終わり。
何度か目のプレイで最終ボスまでたどり着きましたが、そこであえなく撃沈。
今後の展望
「非常に難しくクリアもままならない」ゲームではありますが
- デッキ構築
- 敵との戦闘
はやりがいがあり、リプレイ性も十分。クリアを目指してローテーションする気持ちが生まれました。
何より、『GEMINOA』や『Blade Rondo』の提供元だけあってイラストやテキストのフレーバーはとても練り込まれていますし。