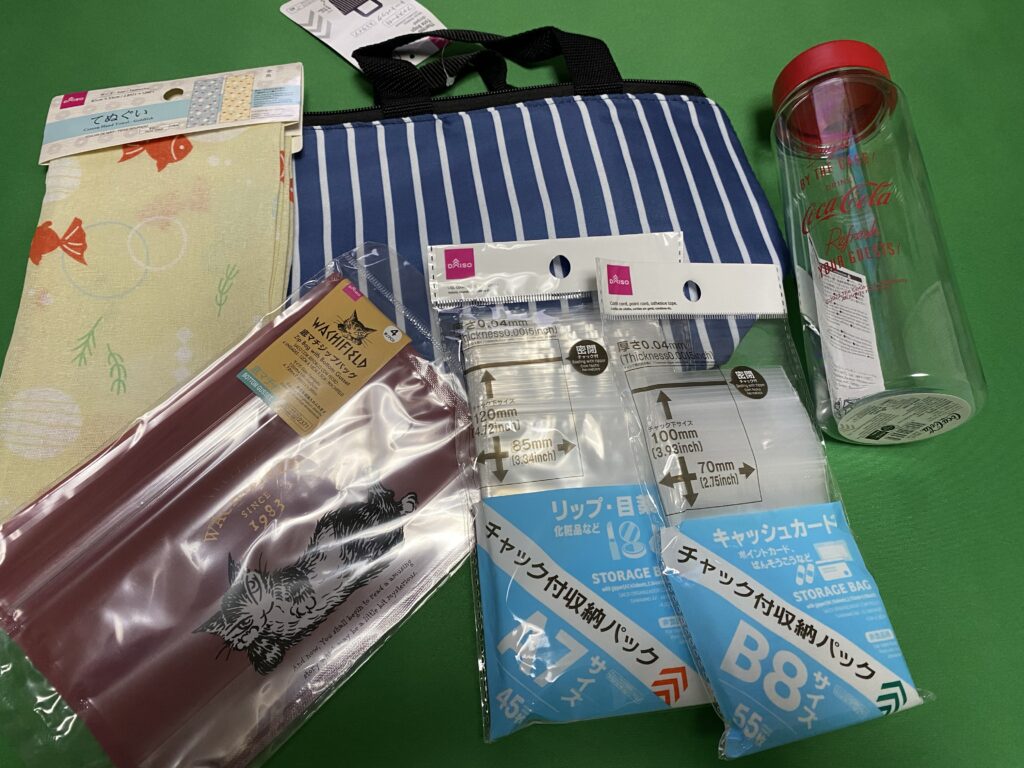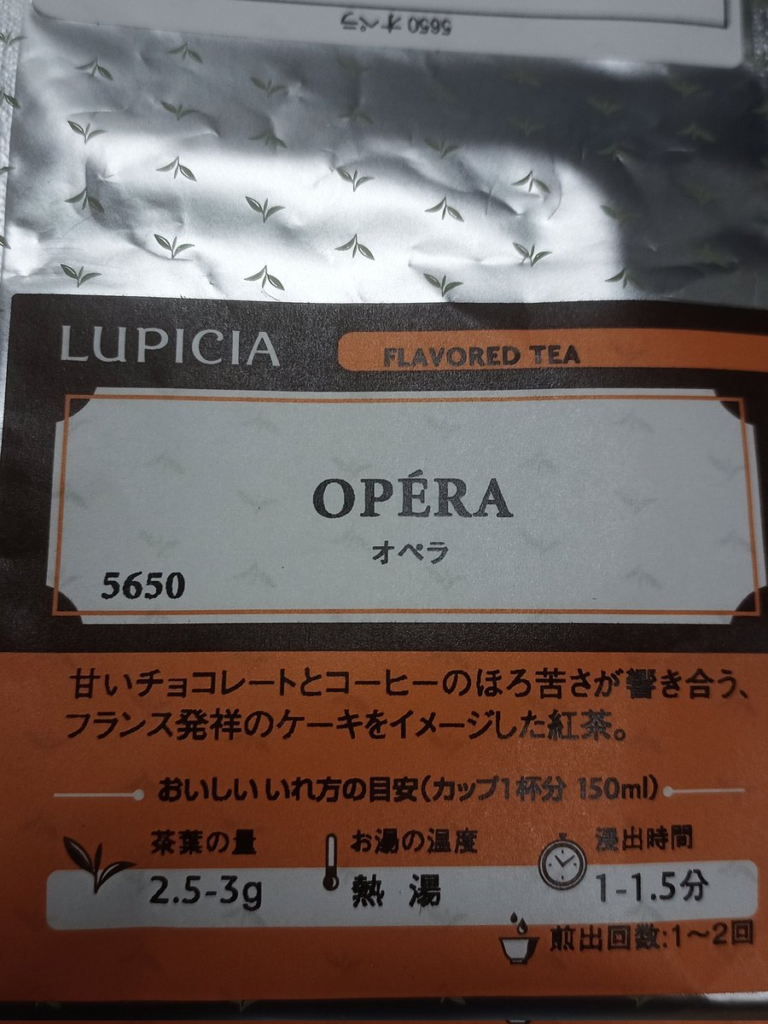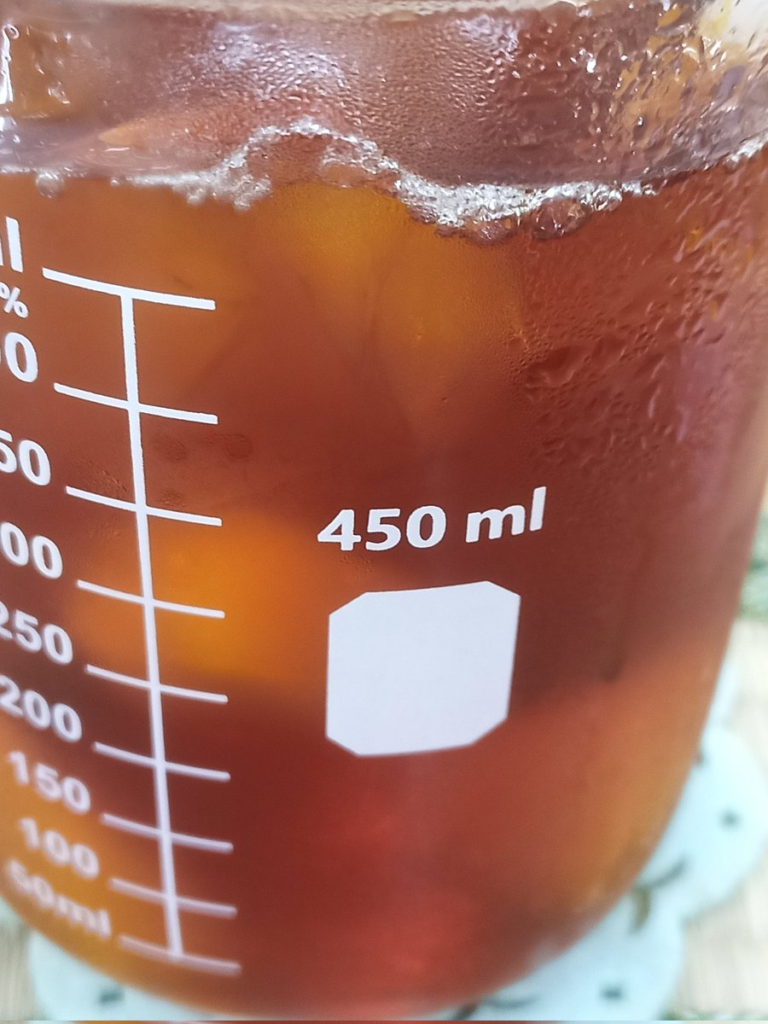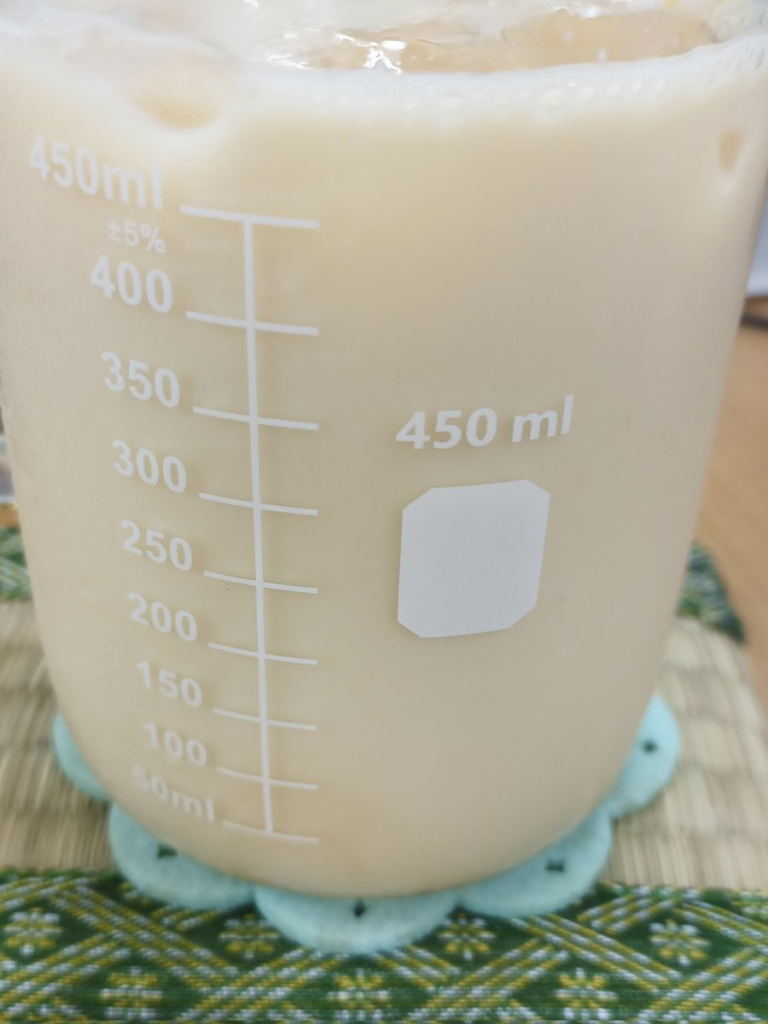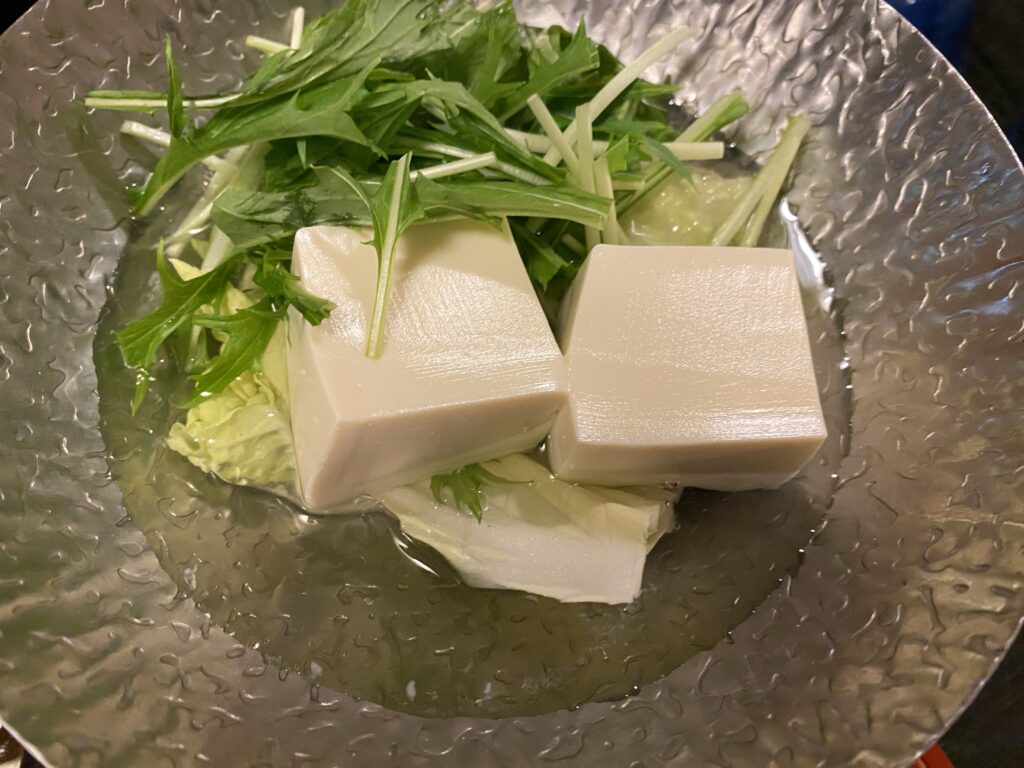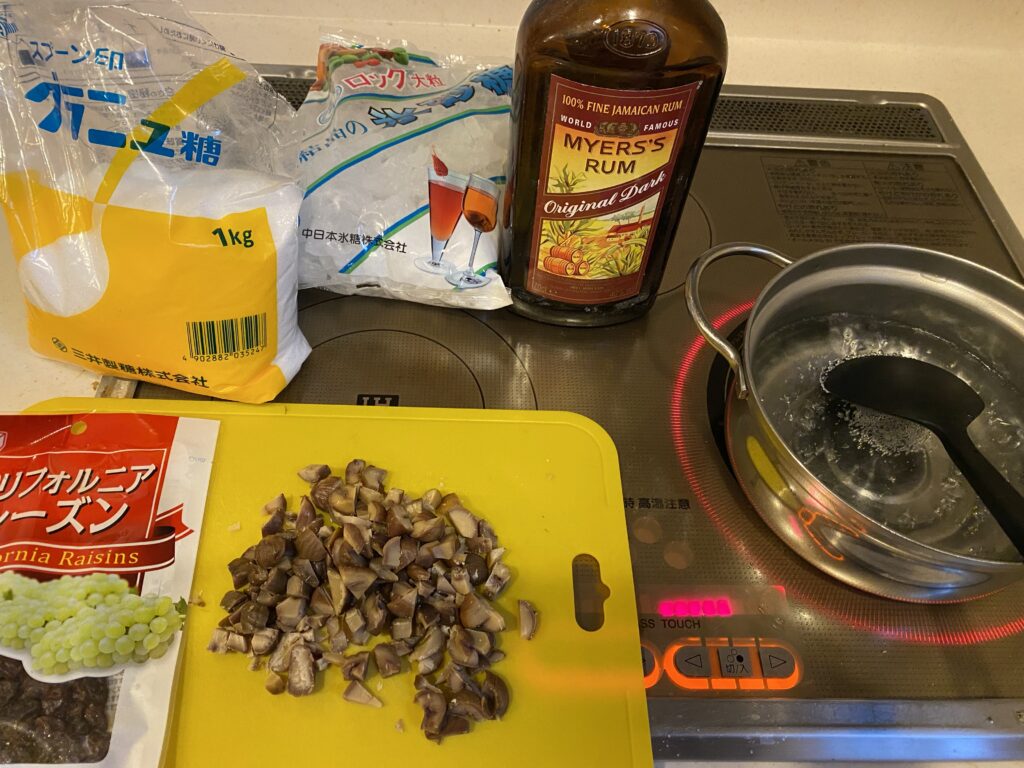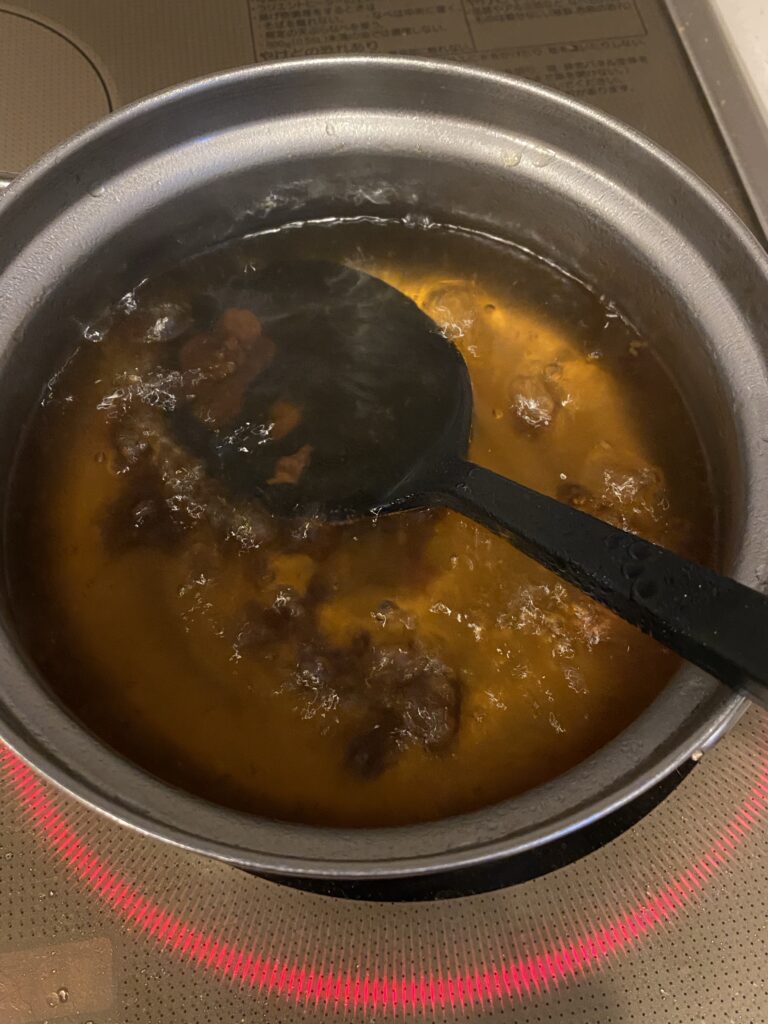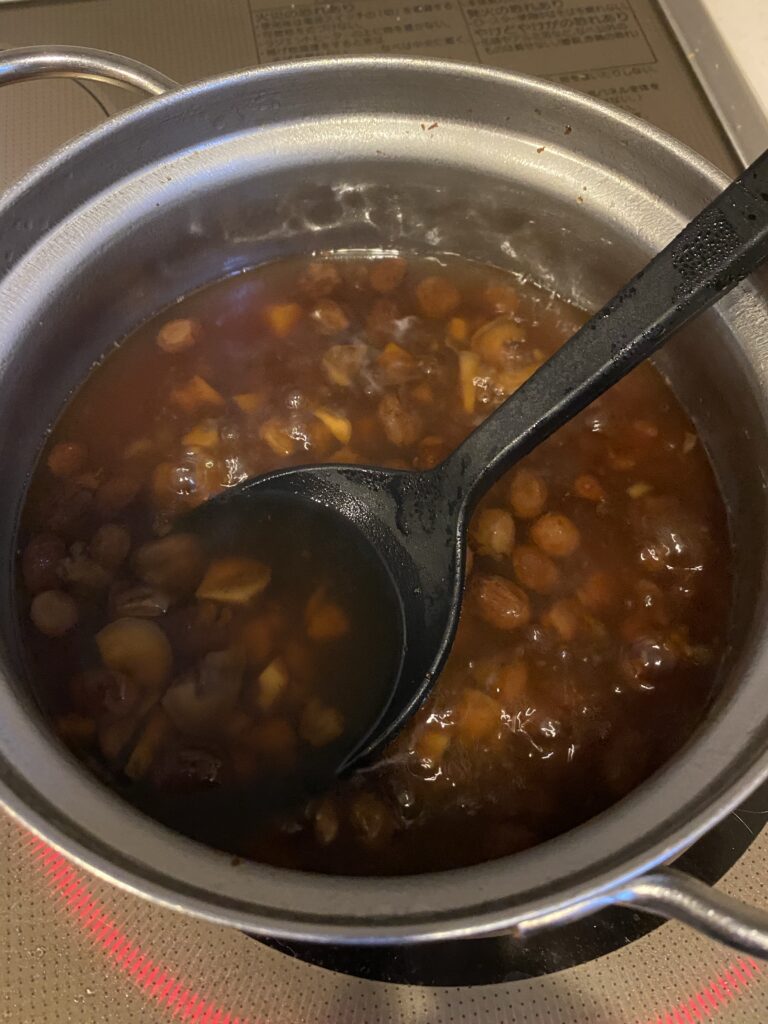概要
昨日の続きとなります。「キチッとした手順でお茶を入れると更においしくなる」と改めて気づいて以来、しっかりとした手順でお茶を入れたいと早見表を作ってみました。
こういうときにmermaidのシーケンスダイアグラムは頼りになります。
シーケンス図
sequenceDiagram
participant m as マグカップ
participant p as ティーポット
participant k as ケトル
note over m,k: 開始
note over m,k: それぞれが清潔な状態であることを確認
note over k: お湯を沸かす
note over p,m: 暖めておく
note over p: 暖め完了
note over p: 茶葉を入れる
note over k: 水沸騰
note over p,k: お湯をティーポットに注ぐ
note over p: 抽出
note over m: 暖め完了
opt ミルクファーストの場合
note over m: 牛乳を注ぐ
end
note over m,p: お茶をマグカップに注ぐ
opt ティーファーストの場合
note over m: 牛乳を注ぐ
end
opt 必要に応じて
note over m: 砂糖などを入れる
end
note over m,k: 完了
どう書いたか
sequenceDiagram
participant m as マグカップ
participant p as ティーポット
participant k as ケトル
note over m,k: 開始
note over m,k: それぞれが清潔な状態であることを確認
note over k: お湯を沸かす
note over p,m: 暖めておく
note over p: 暖め完了
note over p: 茶葉を入れる
note over k: 水沸騰
note over p,k: お湯をティーポットに注ぐ
note over p: 抽出
note over m: 暖め完了
opt ミルクファーストの場合
note over m: 牛乳を注ぐ
end
note over m,p: お茶をマグカップに注ぐ
opt ティーファーストの場合
note over m: 牛乳を注ぐ
end
opt 必要に応じて
note over m: 砂糖などを入れる
end
note over m,k: 完了
こう、流れを書くときに使えるスクリプトは便利です。