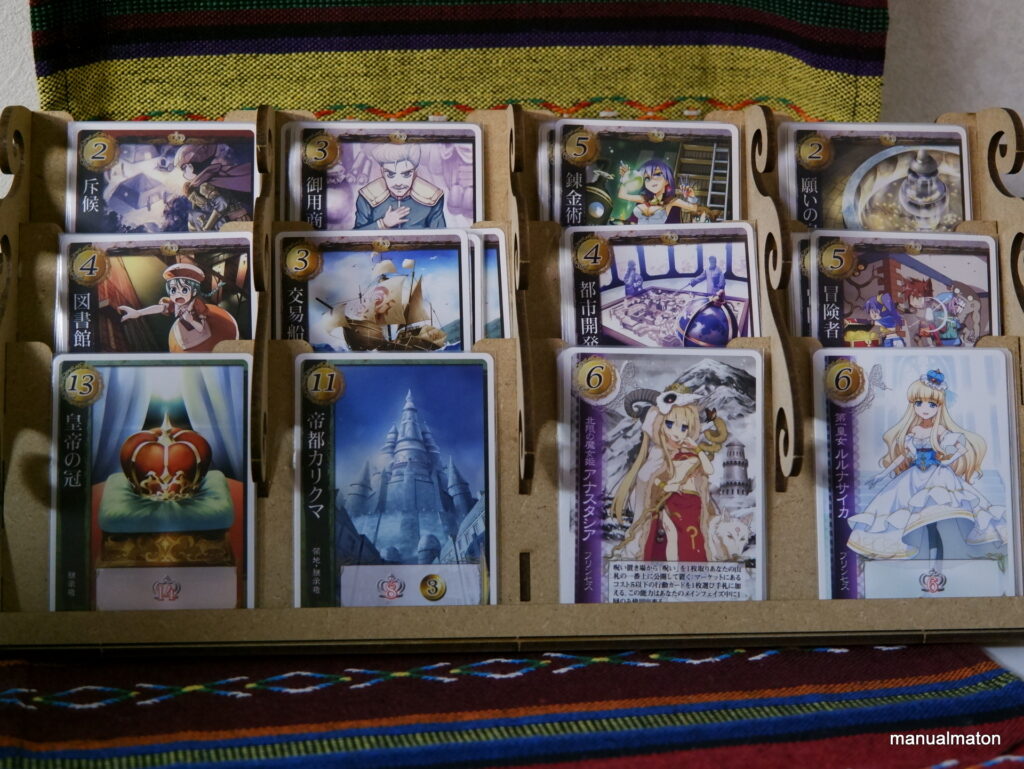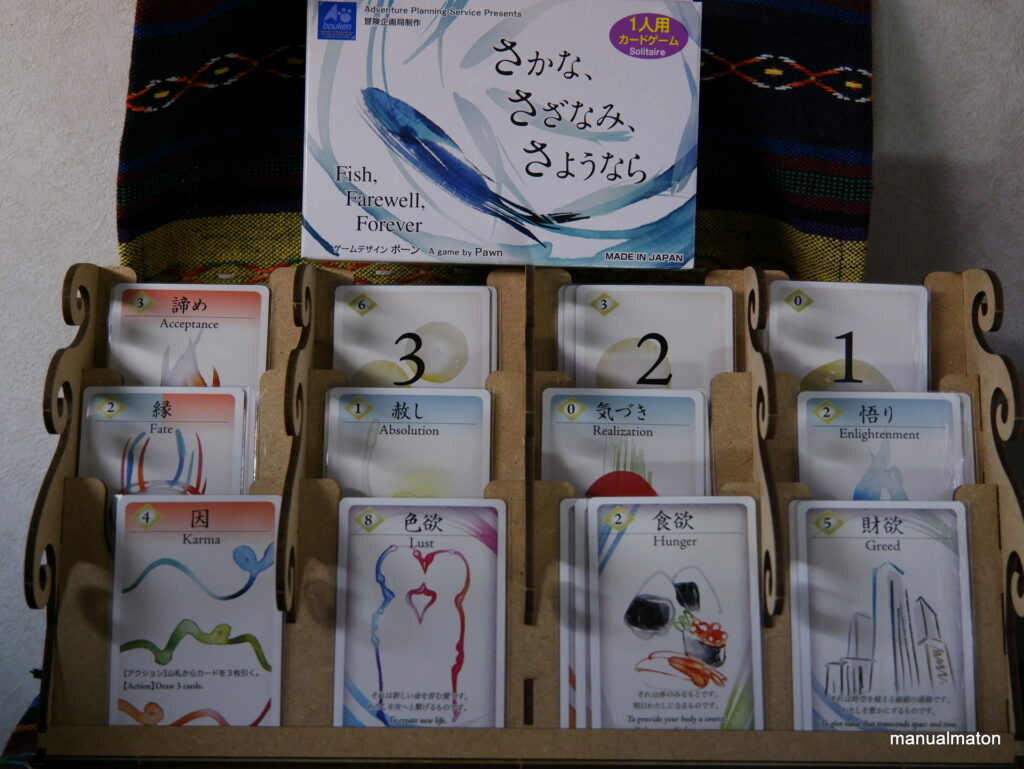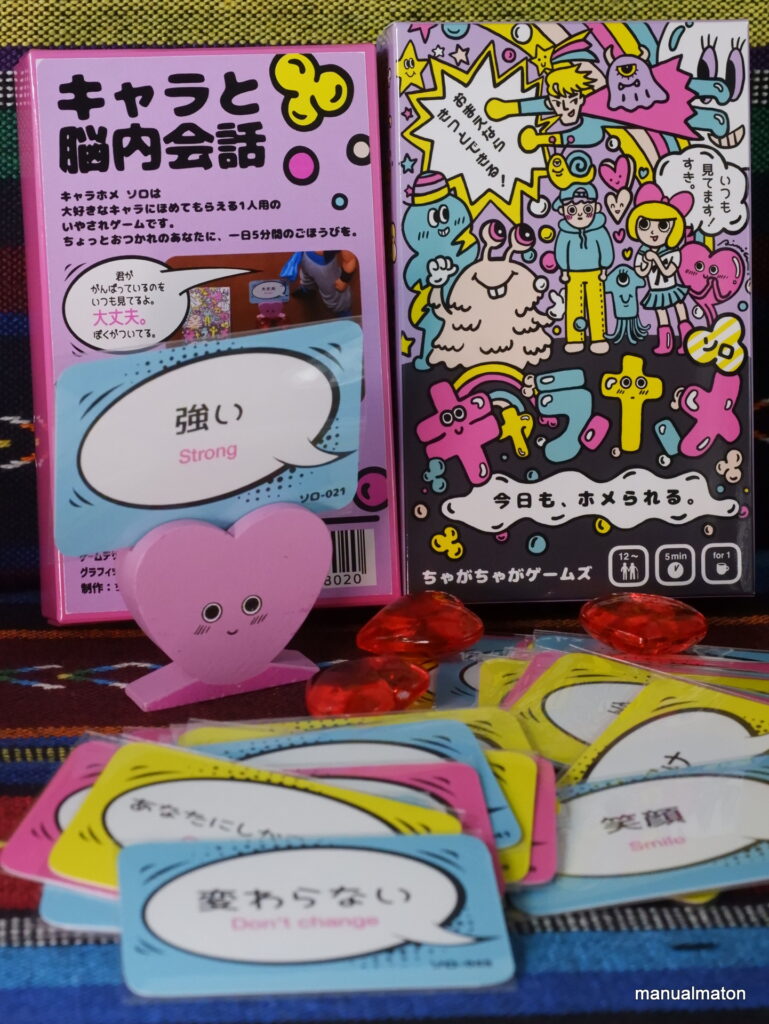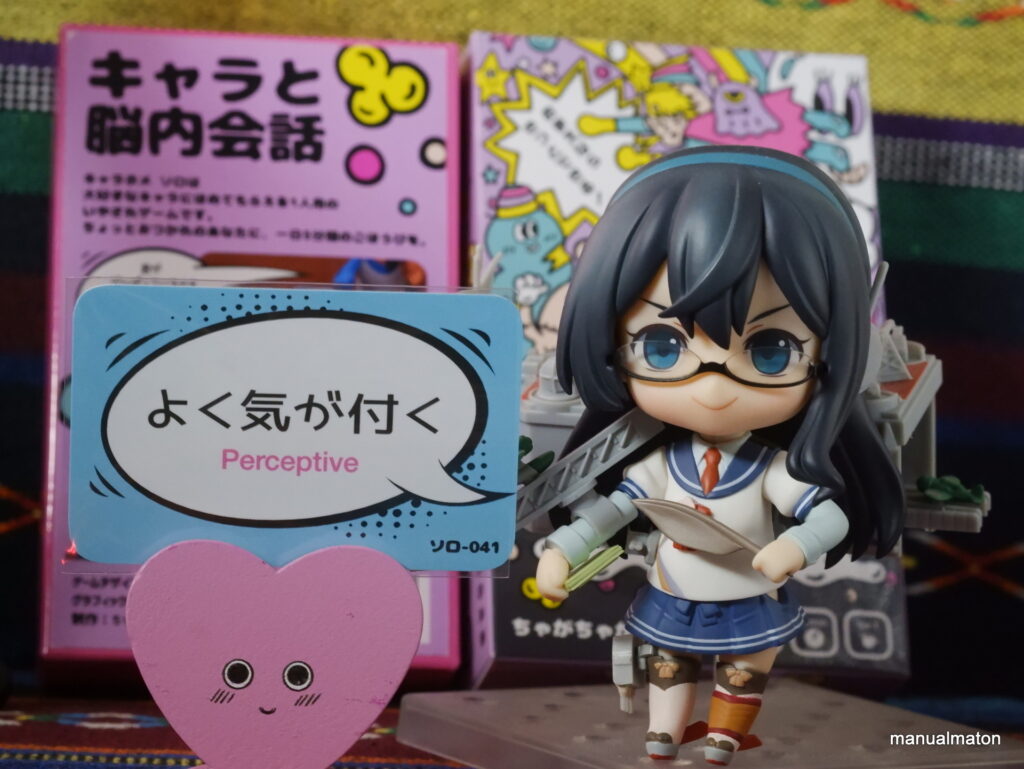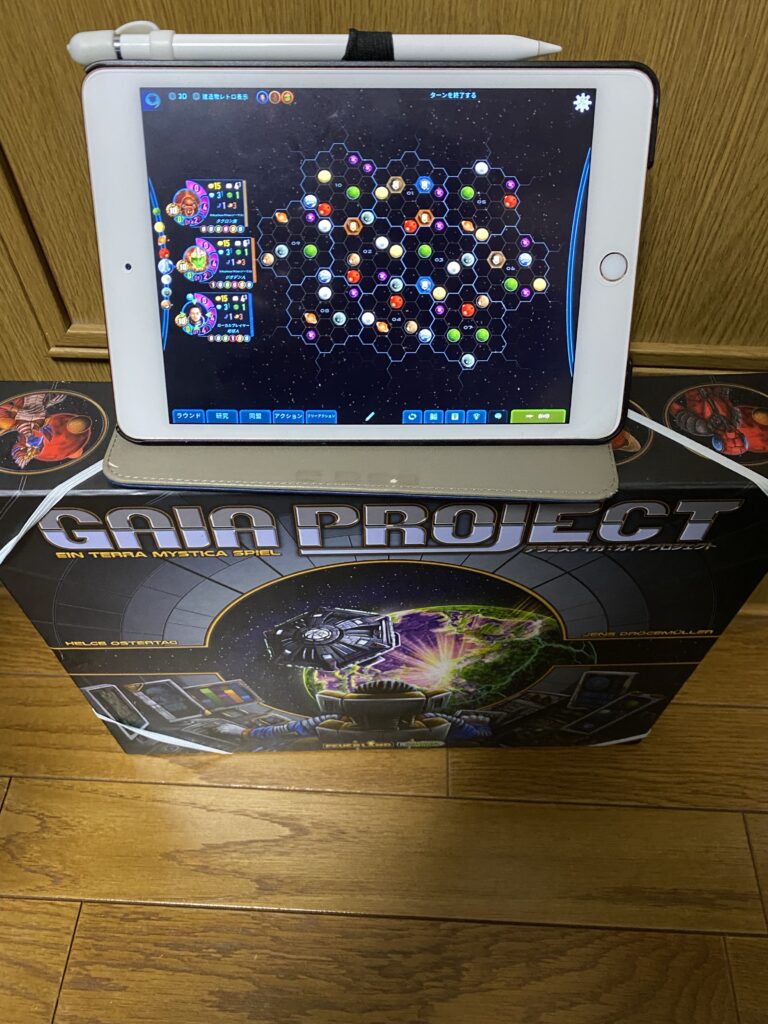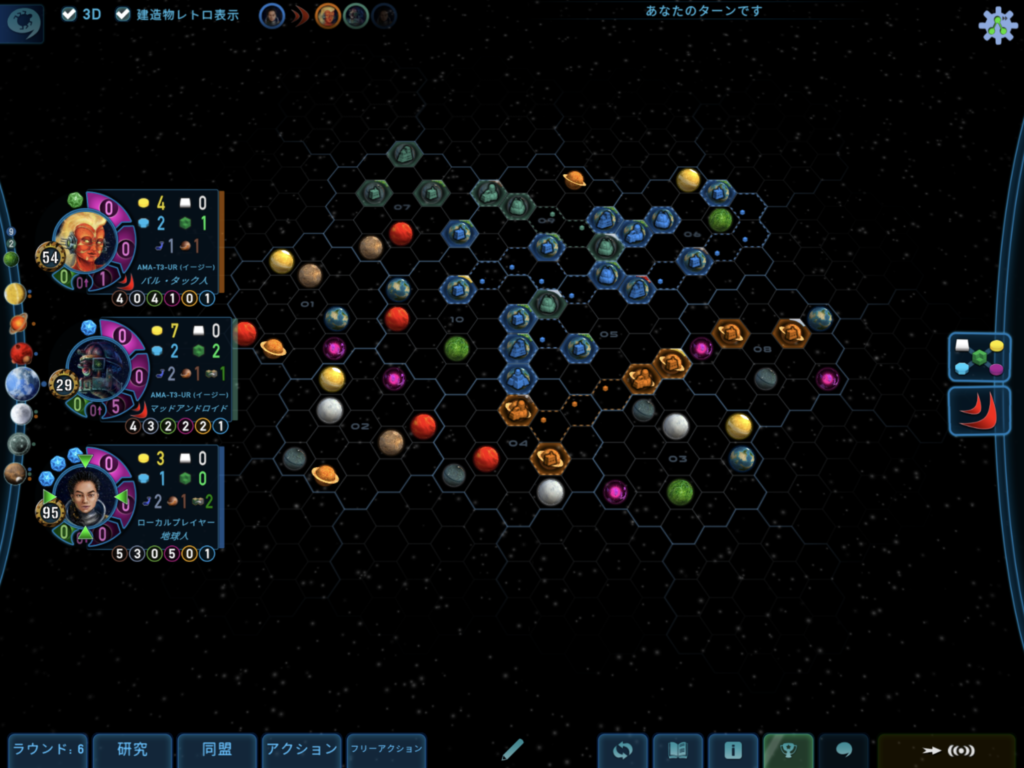徴兵を行うと自分と両隣のアクションに誘発して恩恵があります。早期に行えば行うほどアドバンテージを得られる、「改良」と同じぐらい有用なアクションです。
必要な資源: 食料
- 食料を指定された数だけ消費することで新兵を徴兵します。
- 発動後、両隣の勢力と自分自身が対応した下段のアクションを実行したときに誘発し、ステータスなどが上昇します。
- 改良→戦力が1上昇
- 展開→1コインを得る
- 建築→支持が1上昇
- 徴兵→戦闘カードを1枚得る
徴兵ボーナス
- マット下部にある円筒を取り去り、ボーナスが書かれたところに円筒を置きます。そうすることで、以下のいずれかが「一度だけ」得られます。
- 戦力2
- 支持2
- コイン2
- 銭湯カード2
徴兵誘発の注意点
- 徴兵の誘発は「あなた」→「左隣のプレイヤー」→「右隣のプレイヤー」の順番で発動します。
- 両隣が徴兵を利用しているときは、パラメータ上昇で得られる星章に注意しましょう。
例1) あなたは「改良」を行ったところ、右隣のプレイヤーが改良誘発の徴兵を発動済みでした。右隣は既に5つの星章を獲得していて、戦力は15です。この誘発で戦力が16になり星章は6。その瞬間、ゲームは終わりました。
例2)[例1]と同じような状況ですが、あなたも改良誘発の徴兵を発動しています。あなたの星章も5。戦力も15です。そこで「改良」を行いました。誘発の順番はあなたが先です。なので、6つめの星章はあなたが受け取ります。
徴兵のポイント
これを主軸にすることで、継続戦闘が可能になり、また、終盤の下段アクションを牽制することができます。
特に、クリミアにとってなくてはならないアクションです。