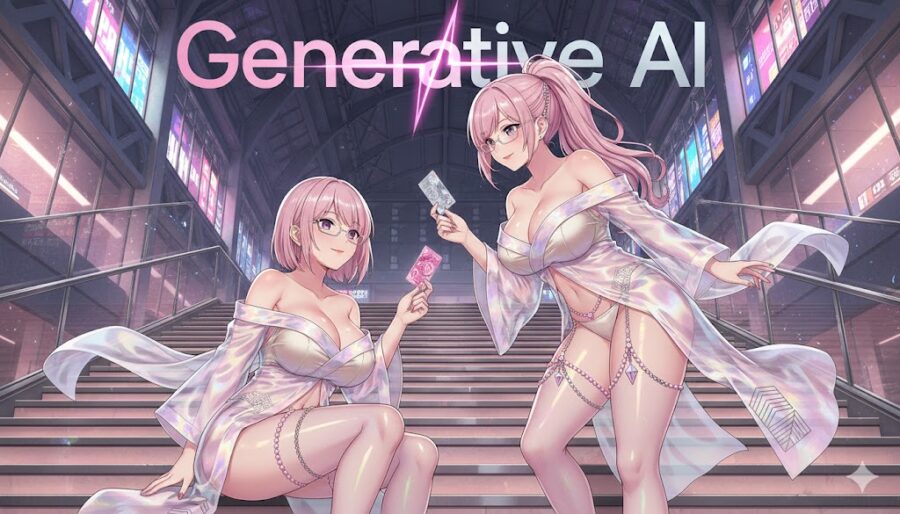※2026年1月現在、本手順は推奨しません。
なぜなら、UFWのルールが複雑になってしまい、ルールが多すぎるとそれだけでサーバのリソースを大きく消費するからです。
(環境が許すならば)の条件付きですが:
上記:ipsetによるufw/iptablesの連携を強く推奨します。
概要
不正アクセス対策として役立つUFW。これによる不審なIPアドレスの遮断をもっと効率的に行うようにしてみました。
このスクリプトを書い(てもらっ)た背景
攻撃者は複数のIPアドレスから同時に不正アクセスをしてくるパターンが多々あり、
ufw deny from xxx.yyy.1.1
ufw deny from aaa.bbb.0.2とやるより、
ufw deny from xxx.yyy.1.0/24
ufw deny from aaa.bbb.0.0/16と、ネットワークアドレスごと遮断した方が効率的だからです。
前提
- 既にUFWが稼働していること。
- サービス指定ではなく、あらゆるアクセスを拒絶するという合意が当事者で取れていること。
ChatGPTへの質問と回答
提示した要件
- IPアドレスを尋ねる
- IPアドレスそのままか、/24ごとブロックするか、/16ごとブロックするかを0~2で質問(空エンターは0)
- 実行前に内容を確認する。yなら続行、nなら中止
- 1~2に沿ってufw deny処理を行う
- 「ルールを付け加えました。他のIPブロックしますか?」の分岐を出す。yなら1に戻る。nなら次の処理
- ufw reloadを行う
- 現在のブロック状況を出しますか? yならufw status numberedを表示。nなら終了メッセージを出す
出てきたスクリプト
- ufw_deny.sh
#!/bin/bash
# ユーザーからIPアドレスとブロック範囲を入力してもらい、
# UFWを使用して指定した範囲のIPアドレスをブロックするスクリプトです。
while true; do
# IPアドレスを尋ねる
read -p "ブロックしたいIPアドレスを入力してください: " ip_address
# ブロック範囲を尋ねる
read -p "IPアドレスをそのままブロックする場合は0、/24ごとにブロックする場合は1、/16ごとにブロックする場合は2を入力してください(空エンターは0): " block_option
# 入力が空の場合はデフォルトで0(IPアドレスそのまま)とする
block_option=${block_option:-0}
# ブロック範囲を計算
case $block_option in
1) block_cidr="/24" ;;
2) block_cidr="/16" ;;
*) block_cidr="" ;;
esac
# ネットワークアドレスに変換
if [[ -n "$block_cidr" ]]; then
if [[ $block_option == "1" ]]; then
# /24で区切る場合
network_address=$(echo $ip_address | cut -d'.' -f1-3)
cidr_notation="$network_address.0$block_cidr"
elif [[ $block_option == "2" ]]; then
# /16で区切る場合
network_address=$(echo $ip_address | cut -d'.' -f1-2)
cidr_notation="$network_address.0.0$block_cidr"
fi
else
cidr_notation="$ip_address"
fi
# 設定内容を確認する
echo "以下の内容でブロックを行います:"
echo "IPアドレス: $cidr_notation"
read -p "よろしいですか?(y/n): " confirm
# ユーザーが処理を続行しない場合、スクリプトを終了する
if [[ $confirm != "y" && $confirm != "Y" ]]; then
echo "処理を中止しました。"
exit 0
fi
# ブロックルールをufwに追加
sudo ufw deny from "$cidr_notation"
# エラーがあった場合はエラーメッセージを表示して終了
if [[ $? -ne 0 ]]; then
echo "ERROR: 不正なソースアドレス"
exit 1
fi
echo "ルールを付け加えました。"
# 他のIPをブロックするか尋ねる
read -p "他のIPをブロックしますか?(y/n): " continue_blocking
if [[ $continue_blocking != "y" && $continue_blocking != "Y" ]]; then
break
fi
done
# ufwを再読み込みする
sudo ufw reload
# ブロック状況を確認するか尋ねる
read -p "現在のブロック状況を確認しますか?(y/n): " check_status
if [[ $check_status == "y" || $check_status == "Y" ]]; then
sudo ufw status numbered
fi
# 終了メッセージを出す
echo "IPブロックを終了しました。"このスクリプトを
chmod +x ufw_deny.shとすれば作成は完了です。
スクリプトの動き
./ufw_deny.sh
ブロックしたいIPアドレスを入力してください:
# IPアドレスを入力します
IPアドレスをそのままブロックする場合は0、/24ごとにブロックする場合は1、/16ごとにブロックする場合は2を入力してください(空エンター
は0):
# IPアドレスのレンジを
# IPアドレスそのまま:0
# /24(255.255.255.0)で区切る:1
# /16(255.255.0.0)で区切る:2
IPアドレス:
よろしいですか? (y/n):
# 先ほどのIPを表示します。ネットワークアドレスの場合は、/24 /16で区切って表示します。
# 内容を確認します。
# y を入力後、ufwの処理が走ります。一般ユーザーの場合はsudoパスワードが訊かれます。
ルールを追加しました
ルールを付け加えました。
# ufw deny from (入力したIP/NWアドレス)を実行します。
他のIPをブロックしますか?(y/n):
# 続行するかを訊きます。yの場合はIPアドレスから始まります。
ファイアウォールを再読込しました
現在のブロック状況を確認しますか?(y/n):
# yの場合は sudo ufw status numberedを実行します。と、
- IPアドレス→ネットワークアドレスへの変換
- UFW DENYに追加
- UFWルールの読込
- 設定後のルール表示
まで一元管理してくれます。