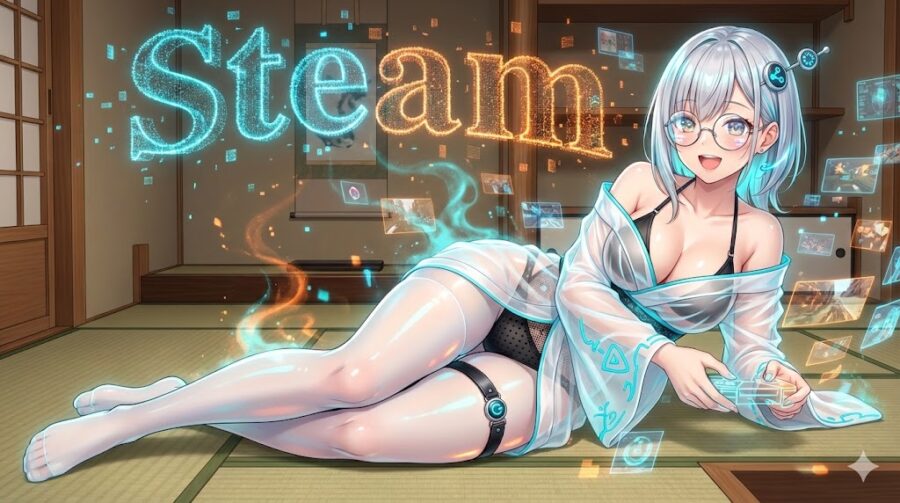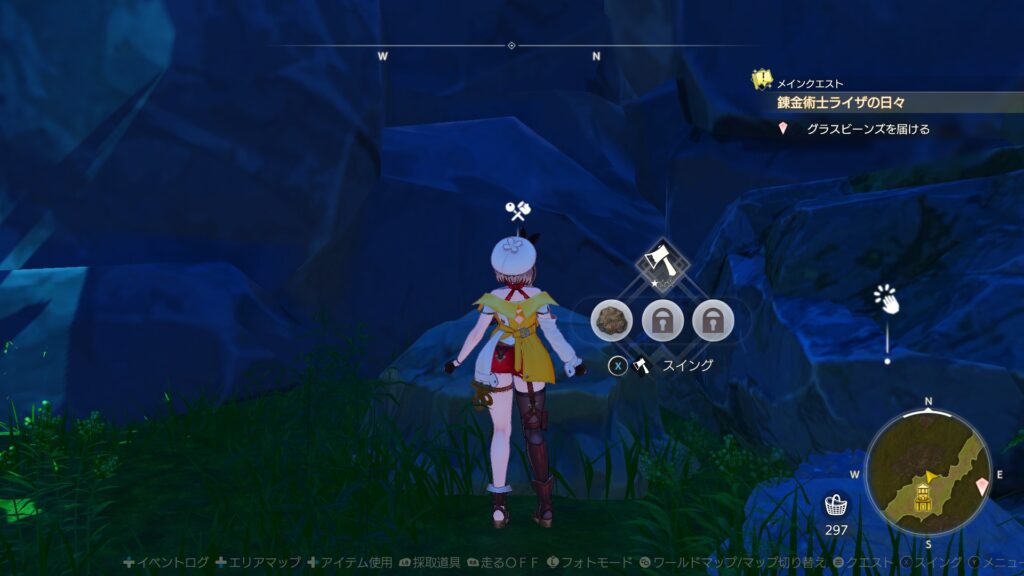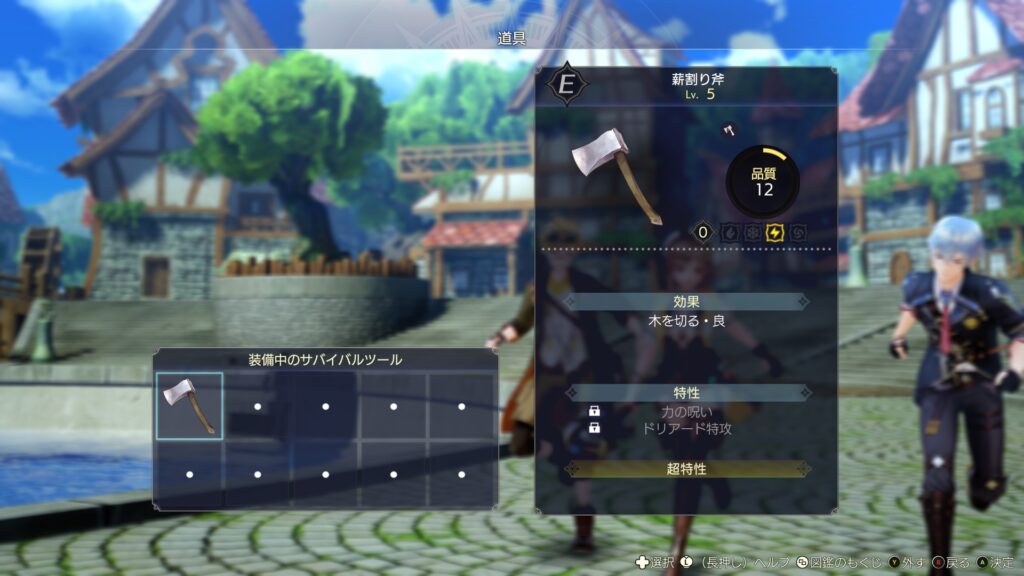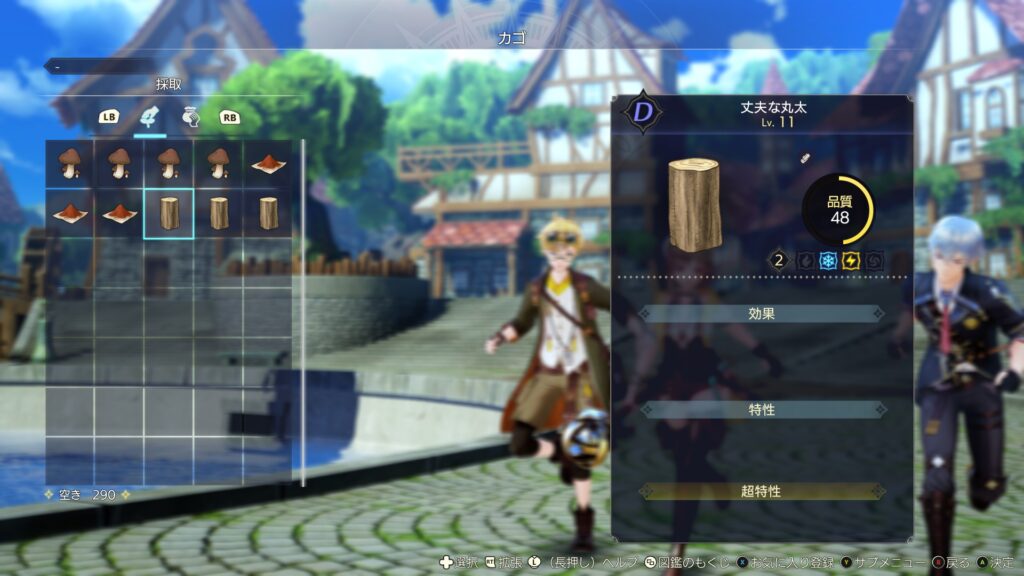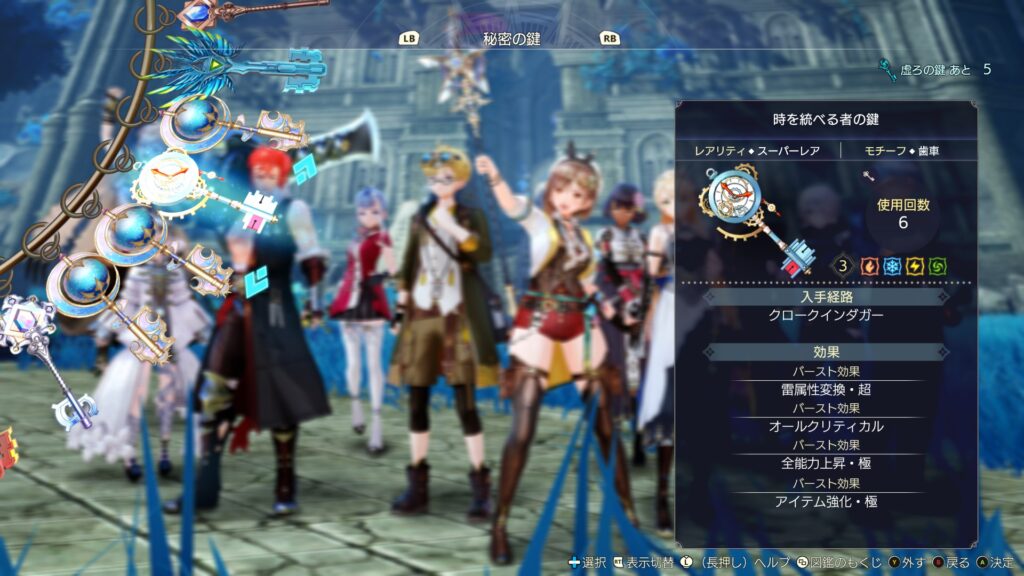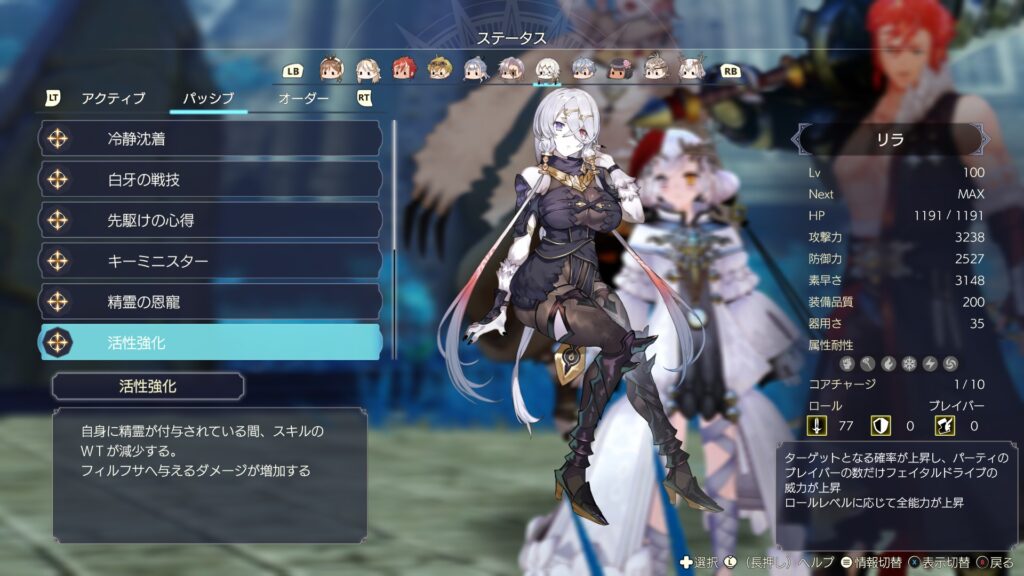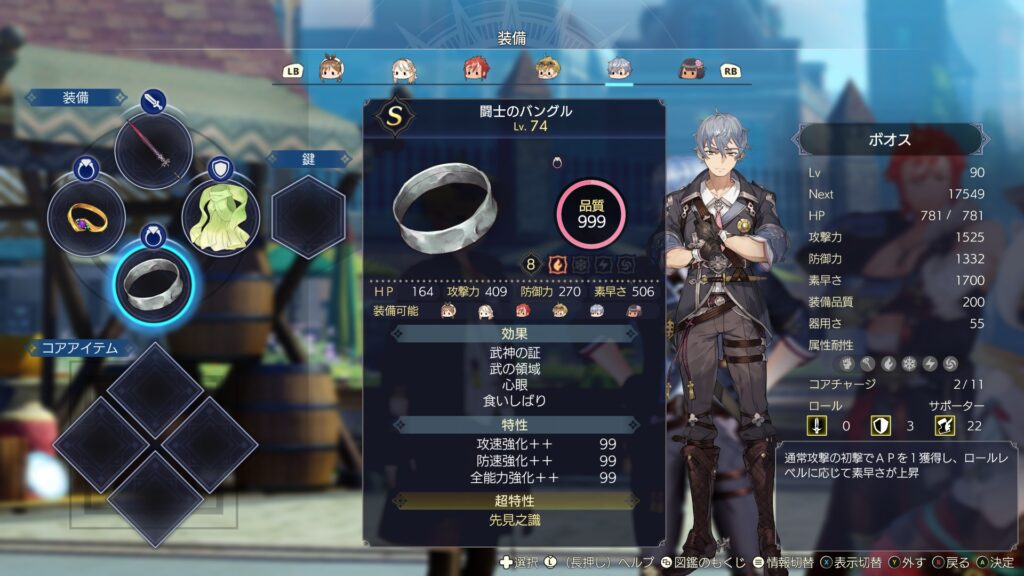この記事の補足事項です。
クエスト「クレリアの想い人」は、特性「自由な魂」が付与された薬品を納品します。
当初、
- 超純水のマテリアル環「気体」にスカイバブルを入れる→薬の材料
- 隠者の軟膏を調合する
手段を執っていました。ですが、スキルツリーの最初の方に出てくる「ヘイズブレス」が遥かにやりやすいので、こちらの手順を紹介です。
調合可能なタイミング
無垢の鍵解禁後の方がやりやすいです。
必須素材
霞石

ランドマーク星見の高台近くにある小岩を斧で採取します。
狼煙草

ランドマーク紅の箱庭にある花から通常採取できます。
スカイバブル

特性付与に使います。ランドマーク尖晶の森から網で採取します。
オプション:水環石

ランドマーク星見の高台近くにある小岩をハンマーで砕きます。(要DLC)
これはリンクコールで使います。
調合

調合メニューから「ヘイズブレス」を選択します。
霞石を入れ、

狼煙草を入れます。

気体スロットにスカイバブルを入れます。

降下2をリンクコールします。「水環石」を代わりに発現。
クレリア地方~ネメド地方を最初に探索する際、全体回復を持つコアアイテムは地味に少ないので重宝します。

残りの効果発現は影響拡大を持つ素材で一気に行いました。

特性に「自由な魂」を忘れずに選択して調合完了。
これで、
- 比較的省CC
- 回復効果を持ち
- 後のクエストにも役立つ
アイテムが完成です。